今回はタランドゥス(タランドス)の幼虫飼育について、幼虫期間や飼育温度、オス・メスの見分け方などを中心に紹介します。
これからタランドゥス幼虫の飼育がしたいという初心者の方向けです。
タランドゥスは国内に入ってきた当初は飼育方法が分からなかったため難易度の高いクワガタでした。
成虫まで羽化させるのは当然難しく、羽化しても小型の個体ばかりという状態。
その後、タランドゥス幼虫がカワラタケの菌糸ビン(カワラ菌糸ビン)で飼育できることが分かってからは難易度も下がり大型個体も羽化するようになりました。
カワラ菌糸ビン
温度管理(20℃~25℃)した環境
上記の2つが揃えば他の外国産クワガタムシを飼育するのとあまり変わりません。
タランドゥスの幼虫飼育はぐんぐん大きく育つため飼育していてとても楽しいですよ。
それではみていきましょう。
※なおレギウス幼虫の飼育方法もタランドゥスと全く同じで大丈夫です。
目次
タランドゥス 卵の管理方法
タランドゥスの卵は緑っぽい色をしています。不思議ですね。幼虫に孵化する直前になると緑色が濃くなっていきます。

卵で割り出した場合は産卵木の木くずをプリンカップに入れて霧吹きで十分に加水します。
そこに卵を置いて孵化を待ちます。乾燥しないように注意します。
割り出したタイミングにもよりますが数日~1週間ほどで孵化します。

孵化直後の幼虫です。真っ白ですね。タランドゥスの幼虫は卵の殻は食べないようです。オオクワガタなどは殻をエサにすることがあります。

孵化から1日ほど経つと頭の色がオレンジに色づいてきます。数日ほど様子をみてカワラ菌糸カップに移します。
カワラ菌糸カップへの幼虫の移し方
まず幼虫が入るくらいの穴を掘ります。
次にそれまで幼虫が入っていた木くずをその穴に敷きます。

そこにスプーンを使って幼虫を入れます。幼虫はとても小さいので傷つけないように注意しましょう。

幼虫を入れたらその上からさらに幼虫が入っていた木くずを覆いかぶせます。


あとはフタを閉めればOKです。
幼虫の食べ具合など様子をみて1ヶ月ほどでカワラ菌糸ビンへ移します。
タランドゥス幼虫の飼育方法
タランドゥス幼虫の飼育で注意すべきは下記の2点です。
菌糸ビンは必ずカワラタケ菌糸ビン(カワラ菌糸ビン)を使用する
飼育温度は20℃~25℃で管理する
菌糸ビンは必ずカワラタケ菌糸ビン(カワラ菌糸ビン)を使用する
タランドゥス幼虫は菌糸ビンでの飼育が適しています。
注意が必要なのが通常のオオヒラタケやヒラタケの菌糸ビンでは飼育できません。
必ずカワラ菌糸ビンを使用しましょう。
発酵マットでも一時的の管理には使えますが成長しませんので長期飼育には適しません。
カワラ菌糸ビンはオオヒラタケと似ていますが上部の被膜が厚くなります。

飼育温度は20℃~25℃で管理する
飼育温度は20℃~25℃が適温です。オオクワガタのように冬眠はしませんので冬季には加温が必要です。
加温飼育が難しい場合にはリビングなど暖房が効いている場所に置いてあげましょう。
夏場の高温にも注意が必要です。こちらも温度管理が難しい場合は保冷剤などを使用して暑さ対策が必要です。
タランドゥスの幼虫期間は半年~1年ほど

タランドゥスは成長が早く幼虫期間が短めです。オスで約8~10ヶ月ほど、メスで約6~8ヶ月くらいが目安になります。
あくまでも目安ですので飼育温度や個体差などによって大きく変わる場合もあります。
初令・2令・3令の区別は他のクワガタムシと同様に頭幅がそれぞれ一回り以上大きく違いますのでそこで見分けましょう。
タランドゥス幼虫に適した菌糸ビンのサイズ

タランドゥス幼虫に適した菌糸ビンのサイズは次のとおりです。(菌糸ビンが大夢の場合)
■3令まで・・大夢カワラ800㏄
■3令以降・・オスは大夢カワラ1400㏄、メスは大夢カワラ800㏄
■オスかメスかはっきりしない場合・・大きく育てたければひとまず1400㏄へ
タランドゥス幼虫は大きな菌糸ビンで飼育すると大きく育ちやすくなります。
3令まではオス・メスの見分けがつかないので800㏄のカワラ菌糸ビンでOKです。3令以降になったらオスは1400㏄、メスは800㏄での飼育で大丈夫です。
3令になってもオスかメスか判断がつかない幼虫は、大きく育てたい場合はひとまず1400㏄へ交換しておけばいいでしょう。
菌糸ビンの交換について

上の写真のようにほとんど茶色い部分になったら新しい菌糸ビンへ交換です。
蛹化するまでの交換回数の目安は次のとおりです。
食べ具合や飼育温度などにもよりますが、タランドゥスは大型種のわりには幼虫期間が短く、温度が高めだと早期に羽化しやすいため2~3回のビン交換が目安になります。
菌糸ビンの交換方法と注意点
タランドゥス幼虫の菌糸ビンの交換方法はオオクワガタなどと同じです。
まず菌糸ビンの上部に幼虫が入る大きさの穴を掘ります。

※カワラ菌糸ビンの被膜は厚くゴムのようになっているためけっこう掘りづらいです。
スプーンを使って幼虫を傷つけないように穴へ入れます。

幼虫を穴に入れたら菌糸ビンのフタを閉めます。※すぐに潜らなくてもフタを閉めてOKです。

あとは20℃~25℃の温度で様子をみて幼虫が潜っていくのを待ちます。

タランドゥス幼虫飼育の注意点
タランドゥス幼虫を飼育する際に注意すべき点です。
■暴れることが多い
■思ったより早く蛹化することがある
どのクワガタムシの幼虫でも暴れることはありますが、タランドゥスの場合は暴れることが多いです。
原因を特定するのは難しいですが、タランドゥスは特に3令以降だとカワラ菌糸ビンの菌のまわりかたが不十分の場合に暴れやすくなります。
そのため菌糸が十分にまわるまで待ってから投入するのがおすすめです。

↑同じ日に菌糸ビンへ投入したタランドゥス幼虫。数日後、右のほうは幼虫が暴れて大部分が茶色くなっています。

タランドゥス幼虫は成長速度が早いです。特に温度が高いと思ったよりも早く蛹室をつくりだすこともあります。
菌糸ビン交換の際には誤って蛹室を壊してしまわないように注意が必要です。
タランドゥス幼虫のオス・メスの見分け方

タランドゥス幼虫のオス・メスの見分け方はオオクワガタ幼虫と基本的には同じです。
ただしオオクワガタに比べると見分けるのは難しい種類になります。
1、卵巣の有無
2、幼虫の体重や大きさ
3、オスのお腹の線の有無
上記の点から判断します。
2令後期~3令になるとメスの幼虫には1対の卵巣が確認できる場合があります。
ただし下の写真のようにタランドゥス幼虫はメスでも卵巣がよく分からないことが多いです。

タランドゥス幼虫の場合は体重で判断するのが一番おすすめです。もちろん幼虫自体の大きさも判断材料になります。

体重でいえば20グラム以上ならオスとみてほぼ間違いないでしょう。15グラム以上ならまずオスの可能性が高いですが超大型のメスという場合もあります。
どちらか判断がつかない場合には1400㏄に投入してしまうのも手です。
タランドゥス幼虫のオスのお腹には縦線が確認できる場合があります。

ただこれもオオクワガタ幼虫などのようにはっきりと見えない場合も多いです。薄かったり無かったり。
あくまで判断材料のひとつの目安にしておきましょう。
まとめ
タランドゥス幼虫の飼育方法について紹介しました。
まとめると次のとおりです。
■飼育は必ずカワラ菌糸ビンでおこなう
■飼育温度は20℃~25℃が適温
■幼虫期間は半年~1年。割と短期間で羽化する
■幼虫はぐんぐん食べて成長する
■菌糸ビンのサイズはオスは1400㏄、メスは800㏄でOK
■幼虫が暴れることが多い
■オス・メスの判別は難しい場合がある
今では特別飼育は難しくはありませんので初心者の方でも十分チャレンジできます。
タランドゥスの場合は幼虫がぐんぐん成長しますので飼育していて楽しいですし、何より成虫がかっこいいです。
アフリカのクワガタですので独特な雰囲気があります。
ただ特殊な種類ではあるので販売店で常時取り扱っているところは少ないのが難点でしょうか。
ぜひ飼育にチャレンジしてみてください。
今日はこのへんで。
それではまた!

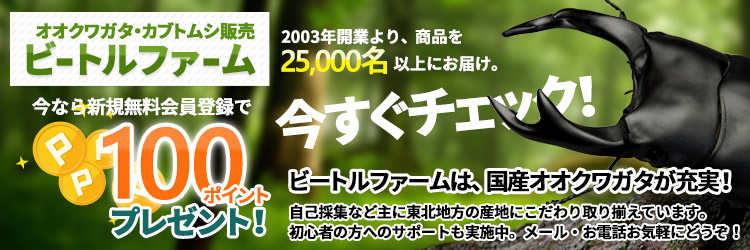
![オオクワガタ幼虫【冬】の温度管理について[冬眠はするの?]](https://beetle-farm-b.com/wp-content/uploads/2019/02/001-3-150x150.jpg)



![オオクワガタ幼虫【冬】の温度管理について[冬眠はするの?]](https://beetle-farm-b.com/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/825-featured-100x65.jpg)









