オオクワガタや他のクワガタムシ幼虫を菌糸ビンで飼育していると『青カビ』が発生することがあります。
初めて幼虫を飼育している方は青カビが拡がっているのを見ると驚くかもしれません。
またどう対処していいのか分からないと思います。
当店でも菌糸ビンの青カビについての質問はたびたび頂きますので。
今回は菌糸ビンに青カビが発生したときの対処法と原因について紹介します。
目次
菌糸ビンに発生する青いカビってなに?
菌糸ビンに発生する青いカビは次の2つの場合が多いです。
アオカビ(青カビ)
トリコデルマ(緑カビ)
それぞれについて少し詳しく紹介します。
アオカビ(青カビ)とは?
日常最も普通にみられるカビで,靴や餅などによく生える。
出典:ブリタニカ国際大百科事典
アオカビは空気中に常に浮遊していて日常生活でもっとも馴染みのあるカビです。パンやみかん等に真っ先に生えるのは大体このアオカビになります。
ブルーチーズの発酵に使われたりもします。
トリコデルマ(緑カビ)とは?
青緑色の粉を吹いたように基物面に広がり、外観はアオカビに似る。トリコデルマ菌には他の菌に寄生する種が多く、(中略)シイタケのような有用菌を攻撃する有害菌もあり、近年、トリコデルマの名が有名になったのはシイタケ栽培に大被害を与えたためである。
出典:小学館 日本大百科全書
トリコデルマは湿気の多いところでよく見られるカビです。「ツチアオカビ」ともよばれカビ毒を発生させます。やっかいなのが他の菌に寄生するところ。
菌糸ビンのキノコ菌糸の生長を阻害するだけでなく、菌糸に取り付いて溶解させてしまうこともあるそうです。
これらのカビは幼虫の害になるのか?
基本的にはカビが少し発生したからといっていきなり幼虫が死んでしまうことはまずありません。
ただしカビが拡がった部分は幼虫は食べませんし、幼虫が大きく育つ手助けをしてくれるキノコ菌がカビによって攻撃されてしまうと栄養を十分に取れなくなってしまいます。
また菌糸ビンの劣化にもつながり、その結果幼虫が大きく育たなかったり死んでしまうケースもあります。
菌糸ビンに青いカビが発生する原因は?

菌糸ビンのキノコ菌が弱っていると青いカビが生えやすくなります。
逆にいえばキノコ菌が強く活発なときにはカビの菌を抑え込むため発生や拡がりを防いでくれます。
菌糸ビンの菌も生きています。時間の経過とともに劣化したり弱ったりします。
カビは空気中などに存在するため完全に発生を防ぐことは難しいです。
もしも青いカビが生えてしまったら状況に応じて対処しましょう。次に対処法について紹介します。
菌糸ビンに青いカビが生えた時の対処法
カビが取り除ける場所なら除いて様子をみる

菌糸ビンの上部にカビが生えている場合は取り除いて様子をみましょう。
内部までカビが続いていたり、側面にまで拡がっていくようでしたら新しい菌糸ビンに交換したほうが良いです。
カビが食痕に少し生えている場合は様子を見る

幼虫が食べたことにより茶色くなっている部分(食痕)にカビが生えている場合はひとまず様子をみましょう。
もしもカビが菌糸ビンの白い部分に拡がってしまうようでしたら新しい菌糸ビンへ交換したほうが良いです。
カビが白い部分に拡がっている場合

カビが白い部分に発生してしまった場合、広範囲(全体の3割くらい)に生えているようでしたら新しい菌糸ビンに交換しましょう。
菌糸が弱っていると白い部分にも生えることがあります。
カビが生えている菌糸ビンを交換する場合は屋外で作業するのが良いです。他の菌糸ビンがある場所でフタを開けるとカビが空気中に漂い別の菌糸ビンにも生える恐れがあるからです。
またカビが多い場合はマスクをして吸い込まないようにしましょう。
まとめ
菌糸ビンに生える青いカビについて特徴や原因・対処法を紹介しました。
まとめると次のとおりです。
■菌糸ビンに生える青いカビは「アオカビ」か「トリコデルマ」が多い。
■菌糸が弱っていると生えやすくなる
■菌糸ビンを高温下や温度変化が大きい場所に置かない
■完全にカビを生えないようにするのは難しい
■カビが生えた場所や範囲によって新しい菌糸ビンに交換する
カビが生えたからといって幼虫がすぐに死んでしまうわけではありませんが、影響が出る場合もあります。
そのためもしもカビが生えてしまった場合は小まめに菌糸ビンの状態を観察してあげましょう。
今日はこのへんで。
それではまた!

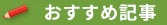
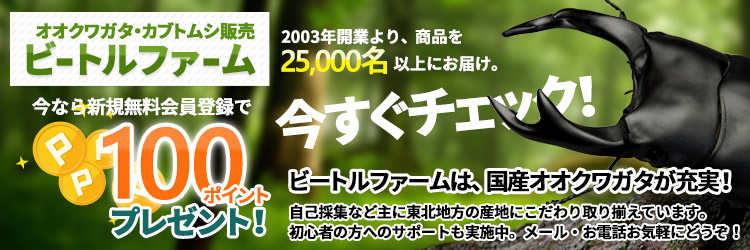




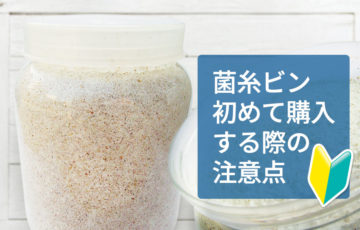




![オオクワガタ幼虫【冬】の温度管理について[冬眠はするの?]](https://beetle-farm-b.com/wp-content/uploads/2019/02/001-3-360x230.jpg)

![オオクワガタ幼虫【冬】の温度管理について[冬眠はするの?]](https://beetle-farm-b.com/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/825-featured-100x65.jpg)









